2010年4月18日日曜日
2010年4月1日木曜日
助詞「は」と「が」の相違の統一的説明
~主体と客体の一般理論~
キーワード:助詞,「は」,「が」,主体,客体
要 旨
国語文法上の難問である,助詞「は」と「が」の違いについて,主にこれが一つの対立から生ずるものであることを解明した。 本稿において,両助詞の相違について,これまでの言語学上の発見を踏まえ, 一つの理論を用い統一的に説明する。
その理論をここで「主体と客体の一般理論」と呼ぶことにする。「一般」とは特殊でなく,「あまねく当てはまる」の意である。この理論をもとに,「私は..., 私が...」から始まり,「既知と未知」,「対比と排他」,「係助詞,格助詞」,「現象文と判断文」,「主題」,「『は』のピリオド超え」,「『は』の兼務と代行」などの各問題を統一的に説明する。結論をいえば、助詞「は」と「が」の相違点は,「は」は受ける語を主体として扱い,「が」は受ける語を客体として扱うというところにある。
1 はじめに
本稿は,助詞「は」と「が」の相違について,言語学上の主要な問題を含め統一的に説明するものである。前半は,私自身が論考を重ねた過程をそのまま文章にした。
2.1 力の方向
私が疑問に思ったのは,この「は」「が」二つの助詞が微妙に違う雰囲気というか,力の方向というべきものをもっていて,その正体は一体何か?ということであった。この論文の本旨はその未知の力の解明にある。今更ではあるが以下の二つの文を比べて頂きたい。
a. 私は...
b. 私が...
「は」と「が」の違いついて,単純な相違を発見できるだろう。そしてその単純さにも関わらず,文が複雑多様になるにつれて,説明の困難さに直面するのではないだろうか?しかし,この単純な相違こそが,後の理論展開につながっていく。そのためにねばり強く論考を重ねていかねばならない。少々幼稚な表現をしていくしかないが,我慢してつきあっていただきたい。
今一度,語感を表現し比べてみよう。
a.は「...は」と言った瞬間に我々の意識の中で,「私」が全体となり,話しが進行していく感覚がする。一方 b.は「...が」と言った瞬間からそれ以降の言葉が「私」に向けて集まってくる感覚がする。
これはあくまで,私の主観に基づくものだが,表現こそいろいろあれ多くの人がうなずくであろうと思う。そして両者の差を強く意識して繰り返し唱えていくうちに自然に,b.については強意(排他)の働きが,a.については「は」を特に強めた場合,「私」以外の他について言及していない事をあえて強く示唆する,いわゆる「対比/とりたて」の働きがでてくる。
この経過から「は」のとりたてと「が」の排他の働きは,それぞれの平叙文での使われ方の延長上にあり,全く別物というわけではないということが分かる。すなわち同根のものであると推察される。
2.2 a.の「は」で観察されたことをまとめると,「は」は「は」で受ける語(私)が
1. 意識の中で全体となり,
その語のもつ意味をもって
2. 意味する範囲を限定し他を排除する,
という働きをしている。
言い方を変えると,「限定しながら広げていく」ということになる。
これは我々が,その語に注意を向ける時に,当然その語のもつ意味を(ある程度)把握するのであるが,我々がその語の意味を把握している,そのまさにその時に我々自身が,その語になる(成り変わる)ということではないだろうか。なぜなら語の意味を広げ,その範囲でもって限定するということが,いかなる他者の入る余地をも残さないということを意味するからである。つまり,「話し手/書き手」,「聞き手/読み手」のいずれもがそこにはない,存在しないということになる。
これは「話し手,書き手」,「聞き手,読み手」という,通常,主体と考えられるものが語の意味内容に入れ代わる作業であるとみることができる。
そこで,この「は」は「受ける語を主体として扱う」とひとまず仮定しておく。
では「が」は受ける語を客体として扱うということになるのだろうか?
2.3 b.の「が」については強意でないときについて,特に考察する必要がある。文脈がなくこのような研究材料として単文の「私が...」の状態では,第一義的に(文を読んで一般に最初にイメージする文意のことを指す...以下同じ)強意で解釈しやすいと思われるからである。(私が,私が,と言うなetc..)
そこで
c. 鳥は飛ぶ
d. 鳥が飛ぶ
d. の「鳥が飛ぶ」の文は目の前に起きた情景を描写するときに「が」は(強意に対し)平静になる。一方c. の「は」は,第一義的には,いわゆる「題目」提示の働きになる。「鳥一般についていえば...」如くの意味になる。
d. の「が」の文は情景描写であるから,「客体として扱うという」理屈に合致しそうである。情景を見ている主体(認識主体)の存在が暗示されているから客体になるという理屈である。
さらに飛んでいる(あるいは飛ぼうとしている)鳥は,明らかに注意の対象である。これはすなわち客体である。
2.4 一方c.の「鳥は飛ぶ」の文は目の前で起きたことを見て話し,かつ平静である場合は,「(既に話題になっているあの名も知らぬ)鳥はどうか?(動きはあるか?)」と聞かれて「鳥は飛ぶ」と答えるとき等の文脈が考えられる。この場合は「鳥」が既に話題になっているので,既知/未知,新情報/旧情報の観点からみて「は」を使うことは合理である。そして「主体として扱う」という観点からはどうか。合理論的だろうか。たとえ目の前の出来事でも,既に話題として取り上げられた場合は話し手や聞き手の主体が容易にその意味するところに合一できるといえそうである。
さらに「は」が強意で,「鳥は飛ぶ」(鳥井は飛ばないが,鳥は飛ぶ)の文の時はどうか。あるいは目の前の「鳥」は「飛ぶ」が同じく隣にいる「鳥井君は飛ばない」等の文脈ではどうだろうか。いずれも強意は主体としての範囲限定の働きが表出したものだ。この場合は主体として扱うことで範囲を限定していることが,受ける語以外の他の可能性を示唆していく。「これについてはこう言えるが,他の事は違うかも知れない」等となる。(これについては後に詳述する)
ところで「既に話題となったことが主体として扱うことを可能にする」ということが本当にいえるのだろうか?
ここで,主体と客体の性質を明らかにしておく必要がある。
3 対概念としての主体と客体の性質
主体とは何だろうか。まっ先に思い浮かべるのが「私自身」である。「私」は主体の最高峰である。
行為主体,認識主体,という言葉もある。だが客観的な立場から,主体を対象として捉えている。これはすなわち客体である。それぞれの「主体」を実は客体として扱っているのである。
では「私」というのが主体だとすると「私」とは何か?「私は身長何センチで」というとこれは私を対象として捉えているので,これも客体である。
しかるに純粋な主体を捉えようとするとできないのである。しかし私がないわけではない。ふだん気がつかなくても腹でも痛くなれば,そこをさすってみる。そこは客体となる。普段は体についている髪の毛でも,切ってしまえばゴミ(客体)となる。
逆に普段は気がつかなくても,あるのが当たり前になっているものは主体(または主体の一部)と言えないだろうか。卑近な例をあげれば,初めて車を入手したとしよう。始めのころはうれしいが,しばらくすると気持ちも冷め,あるのが当たり前になる。やがて何かが原因でそれを失うことになると,今度は無いことの不便に耐えなくてはならなくなる。あたかも自分の体の一部を失ったかのような気持ちになる。
ここで次のことがいえる。
時間的な観点からは,主体は継続を旨とし,客体は変化を旨とすると結論できる。客体も継続すれば,主体(または主体の一部)となり,主体は変化(またはそれを対象として認識すること)をもって客体となる。
そして先に助詞「は」と「が」の働きの中で明らかにしたように,空間的な観点からは対象の範囲を限定しながら全体をそれで満たし,他の一切を排除するということが,主体に取って代わるという意味で主体の性質を獲得する。それは対象とならないという性質もある。客体は,逆に対象となるということである。
さらに客体はもう一つ重要な性質がある。我々は常に多くの変化に直面している。変化それ自体はいわば無数にあり,そのまま全てを認識するわけにはいかなし,できない。渾沌の中から,主に一個の事物に精神を集中させるのである。すなわち一個の客体として扱うということは,その他を意識しつつも,意識の焦点をそこに置くということを意味するのである。
これでざっと主体と客体の説明ができたと思う。これを「は」と「が」に照らし合わせて,繰り返しみていこう。
4 既知と未知
先の件で言えば「既に話題となったことが,主体として扱うことを可能にする」ということはこれで理解できる。
新しく生じたことは客体として発話/記述される。それが話者自身にとっても聞き手にとっても了解済みのこととなり,次に継続する。これは改めて対象(客体)として扱わないかぎり,主体として扱うべき事柄となる。重要な点は「了解済み」であるとして,話者/聞き手自身の内に掌握されているとみなすということが,主体として扱うということになるということである。既知/旧情報であり,主体扱いとなるということは,従って,概ね静かなスタートとなる。「ナントカナントカは...」で始まるのは「ナントカナントカが...」で始まるより静かな始まり方になる。自身の内に既に掌握されているとして,それを動かさずそのままにして表現し,「~は」以下の新しい情報に展開させ,意識の焦点をそちらにもっていくのである。そのため,未知/新情報を何の意味もなく「は」で受けるとおかしなことになる。
5.1 対比と排他(用語は三上章1963)
主体と客体の概念を適用して以下の文の説明をしてみよう。
e. 僕はウナギだ(ウエイトレスに注文をだす等。平静。)
f. 僕はウナギだ(君は天どんが好きだが...等。強意。)
g. 僕がウナギだ(彼が天どんで,僕がウナギで,彼女が何々で...等。平静。)
h. 僕がウナギだ(ウナギが一つだけ注文がありましたが,どなたでしたか?と聞か れて等。強意。)
e. については無助詞の「僕,ウナギ」という文とほとんど変わりない。働きが弱い。だがそれでも主体としての働きが少し感じられる。「僕,ウナギ」に比べて,「僕」に全体性をもたせての話しの進行があるように思う。
f. については主体としての限定的全体性が明らかである。「僕」についてのみ語られると同時に,文自体が(あるいは受ける語「僕」が)客体のように相手方に投げ出されるのである。いわば主体が客体となる瞬間である。これが対比の働きの正体である。すなわち,「は」自体に対比の働きがあるのではなく,限定性を強調する事が,他とのいわばコントラストを作るのである。
g. については,この場合注文内容が現場にいる各自に割り振られていくイメージがある(注文内容が各自一対一の対応を見せている)。現場にいる各自を目印にして,注文を割り付けているのである。これは「僕」を客体として扱う,その他を意識しつつも焦点をそこに当てるというという性質と合致する。e. の「僕はウナギだ」(平静)と違う点は,e. が主体のもつ限定性で他人と注文を混同させることなく独立させているのに対し,この「僕がウナギだ」(平静)は客体のもつ焦点性で,「僕」以外の他人を排除しつつ,注文を「僕」に結び付けているということになる。この主体客体の正反対の原理が,2つの文の文意の微妙な差を生んでいる。
h. については「客体としての焦点を当てるという働き」がそのまま強まったもので,他の誰でも無くという意味である。「f.」と違うのは,「f.」が全体性と限定とをもって発話され,それが直ちに客体化しているので,他については否定も肯定もしていないのに対し,このh. の場合はその他の客体の存在を意識しながらも焦点を「僕」に定めているので,「僕」以外を選択的に排除(否定)をすることになるのである。
5.2 この「対比」の「は」の統一的な説明の難しさは,主体扱いから一転して客体(対象物)となるという,この一点に尽きる。ちなみにh.の文「僕がウナギだ」が逆に主体となることはあり得るのかといえば,これもいとも簡単に主体化する。
(子供がウナギはいやだと言ってさんざん騒いで天どんにしたが,いざウナギがきたらやっぱり食べたくなって)
(ウナギを注文されたのは,どなたでしたか?と聞かれてその子が突然)
「僕がウナギだ」
(と言ったことに対して親が)
「おいおい,『僕がウナギだ』はおかしいだろ」
このように次の瞬間には主体として扱われるのである。客体としては扱わない。ただし意味合いは強くはない。主題程度である。
さらに会話が続いて
(それに対してその子が)
「えっ何がおかしいって?」
(それに対して別の子が)
「『僕がうなぎだ』がおかしいって」...i.
という場合の最終行の...i. は,『僕がうなぎだ』が客体として,焦点となって,新たに話題に浮上させている。これを「『僕がうなぎだ』はおかしいって」に変えても意味は通じるが,「今言った事は了解事項として」「分かっていると思うけど」という意味合いが含まれてくるように感じる。「主体として扱う」ということは,自分達の内に既に取り込まれているという意味合いがあるともいえる。
6 格助詞「が」と係助詞「は」
両者ともに主体客体の対立から,そのそれぞれの傾向が表出したための区別であると考えられる。
6.1 格助詞「が」
客体として扱う「が格」は述語に係るが,概ね「は」に比べて係る範囲が短い。客体の性質故,文を構成する一要素としての役割しかもたない。つまり言語主体の存在を前提とし,それを視点にして,一つの対象物となる。それは例えると文の中で「ナントカが」が客体の一つとして,「ナントカを」「ナントカに」と同じ様に,ちょうどパズルのピースのように組み込まれているようなものである。
そして,「ナントカが」以降の受ける語がさらに客体的な語であると,「象が歩く」などのように,文全部が対象となり,情景を描写する文となる。このように「が」で受ける語とその述語が,情景と同じような世界を構成することがある。ここではそれらを含め,意味解釈の前に文法的に言葉がつくりだす世界を言語世界と呼ぶことにする。
6.2 係助詞「は」
文を終結させる力をもつ係助詞は,実は終結させないとおさまりが着かないからだと考えるべきである。
k. 私は走る時...
l. 私が走る時...
第一義的には,l. は,そのままで,終結できるが,k. は述語が後で出てきそうな勢いがありおさまりがつかないように感じるかもしれない。しかし,
「君は座っている時と走る時のどちらが好き?」
「私は座っている時」
「私は走る時」
のように,文意によるのである。
概ね主体の「は」が終結しずらく長もちしやすいのは,主体としての性質の「継続」があるからである。話者/聞き手自身,全体が「受ける語」に成り変わるということは,「は」以降の説明,語りは単に「受ける語」(自分自身)に脚色を加えていくだけとみることができる。これはどこかで打ち切るか,次の題目提示があるか,忘れるかしない限り,延々と継続してしまうのである。
逆に(名詞文の場合)客体の「が」は効力が短く切れやすい。「が」で受ける語に,次々に述語が修飾するように集約していくため,時間的な継続がない。つまり主体のようにそれ自体を変化させ説明していくのではなく, 客体として,そのままに(認識主体から見て対象のままに)客体に説明を加えるのである。「が」以降の説明,語りが「が」で受ける語に帰趨していくともいえる。このように客体として扱うということは,あくまで「が」で受ける語のその瞬間あるいは対象としての立場に留まるのである。(動詞文については次の「7現象文と判断文」にて詳述する。)
7 現象文と判断文(用語は三尾砂1947)
c. 鳥は飛ぶ
d. 鳥が飛ぶ
先の動詞文についてもう一度考察したい。第一義的には「鳥は飛ぶ」は判断文であり,「鳥が飛ぶ」現象文とみてよいと思う。この種別が主体客体の区別から生ずることはもはや説明を要しないであろう。「鳥は飛ぶ」の「鳥」は主体として扱われるが故に,文脈を与えられない条件では,聞き手自身の中の鳥の一般的な概念が適用される。「鳥が飛ぶ」の「鳥」は客体としての「鳥」であり,それは,情景描写が最も頻度が高いため,第一義的には現象文となる。
問題は,現象文の「鳥が飛ぶ」の「鳥」が客体として扱われているのにも関わらず,平叙文としてあることにある。第一義的には名詞文の場合,5.1で述べたように主語に焦点が集まりやすい(ぼくがウナギだ...などの強意)のに対し,動詞文では平静である。これはなぜだろうか。
それは一般に情景を描写する現象文の場合は,概ね全ての語が客体としてあるからである。主体の側につく語がない。つまり,了解事項としてなく,主語述語ともに新しい情報としてあるからである。それが現象文の平静さをつくりだすのである。
一方の c.「鳥は飛ぶ」は「鳥」というものに意識を合致させ,それが「飛ぶ」という動作に係ることにより,「主体の鳥」が「飛ぶ」形になる。そこには動作を観察している主体(認識主体),あるいは視点の中心というものがなく,主体が「鳥」となり,また「鳥」が主体となるという状況になる。これが判断文を構成する。だが「鳥」という語の意味解釈によって文の種類が変わる可能性がある。確かに「鳥一般」についていう場合と,目の前の「鳥」についていう場合は判断文となりやすい。しかし判断文と呼ぶことには疑問が生ずる場合もある。例えば「鳥」が主人公となる物語の中での「鳥は飛ぶ」を想定すると,「鳥」という主体にもっと近付く。自身が鳥となり飛ぼうとする意志が感じられる。それは「判断文」という名称に相応しくない。またその時の「鳥」は「題目」「主題」とも呼べない違う種類のものとなると思う。「~について言えば」の心持ちではなく,もっとダイレクトな,「言語主体=飛ぶ」ぐらいの心持ちである。いずれにせよ,主体という観点からは明確に説明できる。
8 主題とは何か
提題の助詞としての「は」の正体は,主体として扱われるもののうち,とりたての働き等を除く,受ける語を既に自身の内にあるとする,いわば既定的,前提的働きをもたせるものである。「~について言えば」と扱われる場合がそうである。受ける語は主題として扱われるが,それは主体としての働きの一つである。
これを我々が「主題」と考えるのは,このようなわけである。例えば,文章などで,一貫して流れるものをテーマ(題)とか,あるいは文章の固まりを一つのトピックと呼ぶことがあるが,これこそが我々が,既にそれを客体(対象=読んでいる文)としてではなく主体として,あるいは主体の一部として,自身の内に掌握し,変転する文自体と関わりながらも一貫して変化せず継続していくものとみなしているものである。提題の「は」は,受ける語を主体として扱うことで,同じ作用を及ぼす。そのようなわけで,「主題」という言葉がよく当てはまるのである。
9 主語の省略 ...「は」のピリオド超え
「は」で受ける主語は省略されることが多いとされる。だが次のような場合は省略しないで言うと,逆に不自然となることが多い。
「私はケーキが好きです。そして私はプリンも好きです」
これは2番目の「私は」は排除しなければ,不自然になる。
「私はケーキが好きです。そしてプリンも好きです」
これはこの文のみを観察すると,2番目の主語の「私は」 は省略されていると解釈せざるを得ない。しかしながら主体という考え方からすると,省略ではなく,文を扱う主体の側に取り込まれたので,一文を超えて運用されているのだと考えることができる。ここにおいて,助詞「は」がピリオドを超えるという振るまいの正体が明らかになったと思う。助詞「は」は受ける語を言語主体に託すのである。言い換えると「は」は「言語を扱う主体(言語主体)を動員することを前提」としている助詞といえる。
10「は」の兼務と代行
「象は鼻が長い」と「象の鼻が長いkoto」
「象は鼻が長い」は「象の鼻が長いkoto」の主格部分「象の鼻が」の修飾語「象の」が主題化したものとみなすことがある。他の助詞「を」「に」等との見事な対応関係と合わせるとそのように考えるのが納得しやすい。(三上章1960から抜粋)
象は,鼻が長い。(ノ格の代行) ← 象の鼻が長い koto
父は,この本を買ってくれました。(ガ格の代行) ← 父がこの本を買ってくれた koto
日本は,温泉が多い。(ニ格の代行) ← 日本に温泉が多くある koto
この本は,父が買ってくれました。(ヲ格の代行) ← 父がこの本を買ってくれた koto
このような格関係を,三上は「は」による代行といった。これを主体客体の原理から考えるとどうなるのだろうか。
10.1 客体として扱う「が」「の」「を」「に」と主体として扱う「は」
これまで「が」を客体として説明してきたが,他に「の」「を」「に」もそれぞれ客体として取り扱うという性質をもっていると考えられる。それぞれ強調すると焦点の語句になり,また言語主体(話者,聞き手など)からは対象として独立して,対象世界たるいわば言語世界にて方向性を持たせる職能をもつからである。
それに対し主体として扱う「は」は強調しても範囲限定の働きしかない。そして前述のような客体のもつ方向性というものが,「は」にはない。対象世界にあるのではなく,自身としてあるのだから,いつも中心たる自分の側にあるとも言える。
この場合の主題化は,それまで客体として扱われていたものを主体として扱うという側面をもつことになる。すなわち,文がそれを中心に置いて,話しが進行していく可能性があることを意味する。言い方を変えれば,その文においてそれを中心とした表現世界が構成されるかもしれないということである。くだいて言えば,「この本は,父が買ってくれました」の文は「この本」が主人公の世界を語っているのである。「この本は,作者が原稿を書いて,印刷所で印刷して,問屋さんを流通して,本屋さんが陳列して,それを父が買ってくれました」と書けば,読み手があたかも本になって旅をしてゆく気分にもなるのではないだろうか。
主題化は,そのようにして視点の違う全く別の世界を構成することがあるが,それでも我々は無題文とそれを主題化した文は,少なくともその意味するところは同じであると考える。我々がこれを同じ意味と考えるわけは,それが,特定の視点の中心点をもたない一般的世界観(客観的世界存在)に還元すると同じことを表していると考えられるからである。従って「が」「の」「を」「に」の「は」の代行は一般的な意味の上でのことと考えられる。
10.2 「が」は...
「が」も主題化によって,違う世界観を構成するが,文の内部において,すなわち,「言語世界内」において,「は」と同じ方向性を有する場合が多いと考えられる。すなわち,文中で「中心として話題の展開の前に」あるということである。「が」で受ける語は言語主体から見て客体としての位置にとどまるが,その文内部では述語の説明や動作や状態の中心主体となるのである。これが主格の「が」である。(述語はこれに変容を加える。)
一方の「は」で受ける文は,言語主体を含む形で,あるいは言語主体を消滅させた形で,同じく言語世界の構成で,話題の中心となり得る。だが「は」の中心性は「が」のそれとは異なる。「が」が「焦点性」であるのに対し,「は」は「範囲限定性」の話題の中心ということになる。概ね捉える範囲が広くなりやすく,「は」で受ける主語のような主題のようなものが複数存在しても自然な文を構成しやすい。
10.3 主体の「は」
「は」は,「範囲限定性」とそれと性質を同じくして「言語主体の合一性」をその特徴とすると考えられる。文の係り具合についていえば,「陳述に係る」,「文節をこえる」,「一文を超える」などは,そこから派生するものである。
日本語は助詞によって語の並び順が比較的自由にできる。自由な分,助詞の働きは重要になる。助詞のうちの「の」「を」「に」等が方向性をもつのと同じようにして客体扱いで主格を受ける「が」がある。だがこれだけでは我々の普段持つ世界観の片面を強調する結果となってしまう。この片面とは客観的世界存在のことである。そこで,もう一方の面を扱うために「は」の存在がある。客観的世界存在に対して,主体の存在である。かくして,主体と客体の対立が「は」と「が」の対立によって表現されるのである。これを図式化すると以下の構図になる。
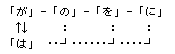
補足1 ...「今日は」について
主題化の一つに無助詞の「今日,何々した」が「今日は,何々した」になるということがある。この「今日」という言葉が主体として扱われることについて触れておきたい。「今日」という言葉が主体として扱われても,決して,これが主人公として中心に置かれるということはない。この場合は主体の範囲限定の働きのみで,言語主体の対象没入が起こりにくい。「今日」という茫漠とした概念には,我々は合致できない。また主題が複数あるような文,例えば「今日は私は晩のおかずは何々にしよう」といった場合も同様,範囲限定のみである。従って上記の世界観の構成には,当てはまらない場合もある。
補足2 ...「今日」の無助詞について
...無助詞で扱う事の多い,「今日」,「昨日」などのうち,「は」を除いて無助詞としてしか扱えない場合がある。例えば,「今日,どこそこで,何々があった。」などという場合である。日本語のリズムから考えると助詞を入れた方が,言いやすいし,聞きやすいと思われるし,実際無助詞といっても,文はここで一拍置かねばならない。だがそれでも,この場合,客体扱いの助詞が使えない。それはこの場合の「今日」という概念が茫漠としているため,「客体」という「意味を特定することを前提」とする助詞を用いるのが不適切であるためではないかと思われる。
補足3 範囲限定の「は」
主体という範疇に「範囲限定」が入るのだろうか。考える順序としては,まず範囲限定が先にあって,それから対象没入,主体化という順序になろう。しかし,主題,主語のような働き方をする「は」は直に主体扱いであるのが実際のところでもある。それは「文法理論があって,会話がある」のではなく,「会話において決まった習慣があって,そこに隠された理論がある」という程度のことではないだろうか。
補足4
そもそも各言葉には意味範囲を限定する働きと,他の言葉との相対的な関係の中での位置的決定(焦点を当てる)の二つの側面があり,「は」と「が」の主体客体の双方の働きはその各側面を抽出しているものだともいえる。
補足5
「は」と「が」の相違は,この理論を用いなければ説明できない。これまで,説明ができなかったのは,この理論が一般的世界観,あるいは一般的世界の成立に先立つものであるからである。すでに世界観が固定されてしまった時点ではうなぎが手から滑り落ちるように,解決が着かなくなる。すなわち固定的な主体「発話者,観察者等」と客体「解析対象=文,文脈」という世界存在にとらわれていてはいつまでも堂々巡りで終わってしまうのである。客体のみの観測では,説明できない。時枝誠記は「即ち言語を観察しようと思う者は,先ずこの言語の主体的立場に於いて,彼自らこの言語を体験することによってのみ,観察することが可能となることを意味するのである。」という言葉を残している。(時枝誠記 1941 p29)
この理論の要は「言語と言語を扱う言語主体」という枠組みを取り払い,もう一度根底から「自と他」の枠組みを作り直し,秩序を構成することにある。
「は」と「が」の相違を考察するうちに期せずして妙な理論が出来上がってしまった。この「主体と客体の一般理論」は,一般に人間が思考(会話,書記等)する上での基本的な法則なのではないかと思う。
すなわち,我々の存在自体,主体と客体の対立によって成り立っているという考え方ができるのではないだろうか。考えるに,「私」という主体もそれに対立する外界があってのことである。その主体たる「私」も常に恒常であるということはなく,また外界も変化する。主体は外界を客体として認識し,それも主体となる。主体も変化し,客体となる。
...そのようにして,主体と客体の対立は連続するのである。
11 結論
助詞「は」と「が」の相違点は,「は」は受ける語を主体として扱い,「が」は受ける語を客体として扱うというところにある。この場合の主体客体は一般的世界観成立に先立つ,一般理論としての対立概念である。
引用(参考)文献
小池清治, 赤羽根義章 2002 「文法探究法」朝倉書店
寺村秀夫 1991「日本語のシンタクスと意味III」くろしお出版
三尾砂 1947 1965 「三尾砂著作集」〈1〉 ひつじ書房
三上章 1953 「現代語法序説」 くろしお出版
三上章 1960 「象は鼻が長い」 くろしお出版
三上章 1963 「日本語の論理」 くろしお出版.
野田尚史 1996 「「は」と「が」」 くろしお出版
堀口和吉 1995 「「~は~」のはなし」 ひつじ書房
時枝誠記 1941 「国語学原論」 岩波書店
時枝誠記 1950 「日本文法 口語篇」 岩波書店
久野すすむ 1973 「日本文法研究」 大修館書店
小池清治 1994 「日本語はどんな言語か」 ちくま新書